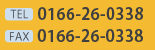講師:旭川医科大学医学部 准教授 戸塚 将
みなさん「理論言語学」という初めて聞く分野のお話しに、戸惑いながらも、刺激を受けたようでした。言葉と言葉の結びつき方や語順による変化など、難しい話に聞き入っていました。最終的に「ことば」をとおして人間の心(脳)を解明する学問との説明に納得?していたようでした。受講生の中には専門的な質問をされる方もおられ、講師の方も感心していました。学生も3名受講していました。
参加者 29名(うち学生3名)
旭川ウェルビーイング・コンソーシアムでは、市民のみなさんの身体的・精神的・社会的な健康の達成と、元気な地域の形成に貢献できるよう様々な活動を行っております。
本講座も生涯教育のひとつとして、単なる知的興味の満足や伝達に終わるのでなくともに地域の課題を考え、地域づくりに取組む契機となることを目指しております。
お気軽に参加ください。(興味のある講座だけでも受講できます。)
定 員: 各講座 30名
募集開始:9月1日(木)から
講義概要 9/23(金)(シニア大学講座室)13:30~15:30
「理論言語学ってどんな学問?」
<概要>理論言語学というコトバを聞くと皆さんはどのような学問だと思いますか?実は言葉というものを通して人間の本質について探求する学問です。実際にどのようにしてその探求を行っているのかを簡単にですが紹介できたらと思っています。ことばに興味がある方もない方もぜひ参加してみて下さい。
講義概要 10/22(土)(シニア大学講座室)13:30~15:30
「三浦綾子記念文学館/その建築と環境」
<概要>小説「氷点」,「塩狩峠」,「母」などの作家・三浦綾子を記念する文学館は,1998年,旭川市神楽にある外国樹種見本林の一角に建設されました。文学館の設計に携わり,現在,同館の副館長・環境整備委員を務める立場から,作家の生誕100年にあたる今年,改めて<建築としての文学館>を振り返り,今後の整備方針について考えます。
講義概要 11/5(土)(シニア大学講座室)13:30~15:30
「Let’s Enjoy English Sounds and Rhythm! (英語の音とリズムを楽しもう!)」
<概要>脳を若々しく保つには英語学習が最適です。英語らしい音の出し方、リズムの取り方のコツを学びましょう。早口言葉、マザーグース、ビートルズの歌などを使って英語らしい発声の仕方を体験してもらいます。英語に興味のある方であればだれでも歓迎いたします。楽しみながら英語を口にしてみませんか。
講義概要 11/19(土)(シニア大学講座室)13:30~15:30
「子どもの権利条約を家庭、学校、地域に活かす」
<概要>子どもの権利条約の基本精神は、ポーランドの小児科医、児童文学者でもあったコルチャックが自らは助かる機会がありながら、ユダヤ人の子どもたち200名ほどとともに絶滅収容所への「死の行進」を行ったことに由来するといわれています。この条約における「子ども観」とは何か、現在の家庭、学校、地域にどう活かすかを共に考えてみましょう。
講師:旭川大学 助教 三谷 美江
認知症予防がテーマの講義のため、高齢者の応募が多く関心の高さがうかがえる講座でした。講義の中で、受講者自身が現状をセルフチェックしながら、日常生活に沿った、すぐ実践できる内容も交えての講義に、講義後も多くの質問が寄せられ、健康で豊かに年齢を重ねるための示唆に富むに活気のある楽しい講座となりました。
参加者 38名
お知らせ
当コンソーシアムは夏季休業のため、8月1日(月)から8月5日(金)
までの間、通常業務を休止させていただきます。
期間中は、施錠するため、事務室へ立ち入りできませんのでご注意ください。
なお、事前に会議室等を予約申し込みしている方は、管理室で鍵を借りた
うえでご利用願います。
一般社団法人 旭川ウェルビーイング・コンソーシアム
理事【業務・財務担当】 竹 中 英 泰
◎第2回は「生命倫理」について~医療における人間の生と死の問題―哲学・倫理学の視点から考える~の講義でした。
旭川ウェルビーイング・コンソーシアムの教育コーディネーターである、元名寄市立大学教授 白井 暢明先生による熱のこもった講義に受講者も、最後まで熱心に聴いていました。
冒頭から、哲学者(ハイデッガー)の「人間にとって最も確実な可能性は『死』であるから、はじまり「死から逃げるな!」、人間は死によって本当に人生の意味を開示できると、前向きにとらえる視点から講義が始まりました。
<内容>
医療技術の進歩とともに、人間の生と死の問題を考える「医療倫理」が重要課題となっています。本講義では、安楽死と尊厳死・人工人妊娠中絶・臓器移植と脳死判定などの現代医療がかかえる問題に対し、その背景やさまざまな歴史的事例を通じて、深刻な問題を身近な問題として講義していただきました。「『死』があることによって、一回限りの生を価値あるものあるものとして『死』を受け入れる。」との哲学者の言葉は、受講者に多くの示唆を与えた講義となりました。
受講者 31名
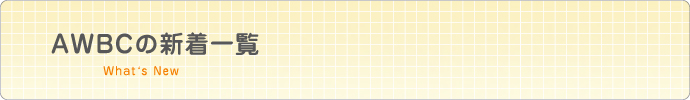
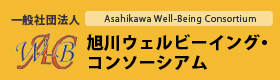
 〒070-0031
〒070-0031