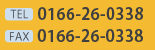2025/11/25 14:43
2025/11/25 14:43
旭川ウェルビーイング・コンソーシアム連携機関の学生が、研究成果・学習成果を発表します。是非ご覧ください。
旭川ウェルビーイング・コンソーシアムは旭川市内の5つの高等教育機関(旭川医科大学,旭川市立大学,旭川市立大学短期大学部,北海道教育大学旭川校,旭川工業高等専門学校)による連携組織です。
成果課題発表(ポスターセッション)
令和8年1月25日(日)午後1時30分~午後4時00分
旭川市1条通8丁目
フィール旭川5階ジュンク堂ギャラリー各課題ポスター前 で順次発表【ご自由に見学ください】
作品展示期間
令和8年1月25(日)午前10時30分~令和8年1月30日(金)午後4時00分
ポスター展示会場
旭川市1条通8丁目 フィール旭川5階ジュンク堂ギャラリー
研究成果・学習成果をポスター形式で展示します。
2025/11/25 14:19
あの「わくわく体験フェス」がイオンモール旭川西にやってくる!
2025年12月6日(土)~7日(日)
10:00~13:00
14:00~17:00
入場無料
2025/11/25 13:51
日時:2025年12月10日(水) 17:00~19:00
場所:旭川工業高等専門学校 講義室(3F階段教室)
プログラム(発表20分、質疑応答10分)
1. 「ミトコンドリア置換法の安全性向上のためのマウス卵ゲノム
凍結乾燥法の試み」 17:00~17:30
講師:旭川医科大学 日下部博一 様
2. 「表現本来のあり方に関する研究」 17:30~18:00
講師:旭川市立大学短期大学部 椎名 澄子 様
3. 「積雪寒冷期間の幼児の運動不足を解消する試み」
18:00~18:30
講師:北海道教育大学旭川校 板谷 厚 様
4. 「テスラバルブ内流れの数値流体解析」 18:30~19:00
講師:旭川工業高等専門学校 石向 桂一 様
2025/11/05 14:20
<概要>
昨今、保育業界では不適切保育という言葉が多く聞かれます。日本における「不適切」の概念は、ここ数年で大きく変わりました。昔の躾は今の時代では虐待と言われかねませんし、その線引きは保育現場でもあいまいであると言われています。何がどうなると不適切なのか?その原因は何なのか?ご参加のみなさんと一緒に考えていきたいと思います。
<講座>
講師自らの幼児教育の経験から、昭和の教育との比較をとおして、幼児期保育の重要性を話していただきました。子どもを一人の人間としてとらえ、ひとりひとりの人権を尊重することの重要性から、将来の労働力としてとらえる教育のあやうさを、強く訴えていました。保育現場にかかわっている若い保育士や管理者の方も参加されており、関心の高さがうかがわれました。
最後に、保育士の処遇改善や保育士の増員による保育の質の改善も急務であることも訴えるなど、保育現場の現状を広くつたえる講座となりました。
参加者 15名
2025/11/05 14:14
<概要>
英語学習者には英単語の学習は避けては通れないものですが、「助ける」という動詞一つ取ってもhelpだけでなくaidにassistと何種類も存在するため、困惑する方も多いかもしれません。さらにbottleやsugarなどの名詞やGoogle、Netflixなどの会社名などが動詞になることがあります。どのような流れから今の英語の姿になっているのでしょうか。英語の語源から見ていきます。
<講座>
国家が形成される過程で、さまざまな民族の言語と交雑し、古英語⇨中英語⇨近代英語⇨現代英語と変遷してきた歴史をわかりやすく話していただきました。語彙や発音からたどる他言語との共通性や地域・身分の違いなど、一つ単語から読み取れる興味深い違いに受講者はうなずきながら聞き入っていました。時代に適応して新たに生まれる言葉の成り立ちなど、実際の会話映像を使いながらの楽しい解説もありました。質疑では、専門的な質問をする受講者もおられ、幅広い方が参加された講座となりました。
参加者 14名
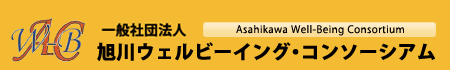




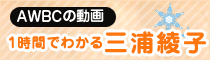
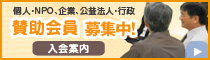
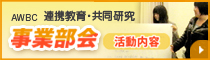


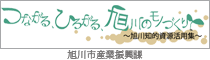

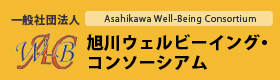
 〒070-0031
〒070-0031